
日本人は昔から樹々には木霊が宿っている、と信じてきた。木霊とは木の精霊であり、樹々のこころであり、八百万の神々の意思ということができるように思う。それを里山の人は、守護神として、八幡宮として、産土神(うぶすながみ)としてまつり崇めてきた。
日本人のアニミズム(地霊信仰)の痕跡は5千年前の縄文遺跡から知ることもできる。その頃の人たちは山に棲んでいた。木の実や根菜が豊富で、森は鳥や獣、魚の猟には最適だった。山を定住の場としたのは、平地は河川の氾濫が多く毒蛇の棲む場所でもあり、安全に暮らすことができなかったからだ。
こんなことに関心を持った理由がある。私は心臓に持病があり、10年以上、2,3カ月に一度は、血液検査と心電図測定と主治医の診断を受けている。2年ほど前になる。主治医は、山と谷とが規則的に並ぶ折り線グラフを示して、見方を説明した。山は数値の悪い状態、谷底は健康体の数値だった。そして、血液の検査結果がわるくなると「山に行け」とすすめた。
浦安と富山の、町と山里の暮らしとを交互にくりかえしている。町の暮らしではスーパーの野菜を食べ、山里の暮らしでは、山菜と山の畑でとれた野菜を食べている。それがそのまま血液検査の数値、[Y-GT]に表れ、山の野菜を食べていると劇的に数値が改善するのである。
「おそらく、自然の中で育った山菜や野菜には、薬膳効果があるのだろう」と主治医は言った。
初冬は枯れ葉舞うときだが、雪国の富山では、氷雨の時雨(しく)れる時節と重なるので、落ち葉を集めることはできない。春四月になって空気が乾燥するころに、落ち葉を拾うために柴刈をしている山に入って、ナラやクヌギなどの落葉を集めて、畑にすきこむ。それに加える肥料は牛糞と油粕、貝灰くらいだ。


そこで、玉ねぎ、ネギ、里芋、薩摩芋、シャガイモ、カボチャ、大和芋などを育てている。山には年に半分しかいないので草むしりはできない。野菜は畑のメヒシバ、ツユクサ、ジゴクノカマノフタなどの野草と競って育つ。
植物の世界は“強存強栄”の超競争社会だ。野菜も自然児として たくましく生きなければ消える運命にある。たくさん、大きな野菜にしようと思ったことはない。産土神の意志に委ねて野菜を作っている。
5月のこと、落ち葉入れた畑に、鹿児島から取り寄せた「紅乙女」の苗を定植した。丸々とした薩摩芋は一杯とれた。つい先日のこと、刈り取りのおわったツルを押切で短く刻んで土に混ぜ込んで、そこに玉ねぎの苗を植えた。



初夏に収穫した玉ネギは、うすく切ってラッキョ酢づけにしておき、毎日の食卓の小皿の一品に加わった。10月に自家製の玉ネギがなくなったので、スーパーで求めた玉ねぎで、同じようにラッキョ酢漬けにしてみた。ごわごわした舌触りで甘みもない。
玉ネギの味は、どれも同じだと思っていたが、まるで違った。薩摩芋と同じ日に収穫した里芋は、甘さも、ねばりも、スーパーのそれとはまったくちがった。

確かに農業経営にはコストと品質の均一化が第一の命題になるだろう。
しかし、その上位に最も大切な使命がある。私の肌感覚だが、いまの乳幼児の5人に一人くらいの割合で食品アレルギーや小児喘息、発疹、精神的な障害をもつ子がいるように感じている。全身に発疹がひろがり、むずがる子を抱いて「ごめんね ごめんね」と朝まで泣き明かしたという母親の言葉が、5年過ぎた今も鮮明に耳に残っている。
殺虫剤や農薬の使用量は世界と比較しても多い。
「農」の、他に代わることのできない第一使命は「健康と安全の保証」である。日本各地の山里も集落の多くは消滅の危機に直面している。それは単に人がいなくなるだけではない。長年培われてきた自然農法の技術が消えることでもある。そして、その技術は再生することが困難なのである。
里山のもつ重要な役割の認知が大きな輪になって広がっていくことを願っている。
ブログ村 里地里山ランキングに参加中です♪

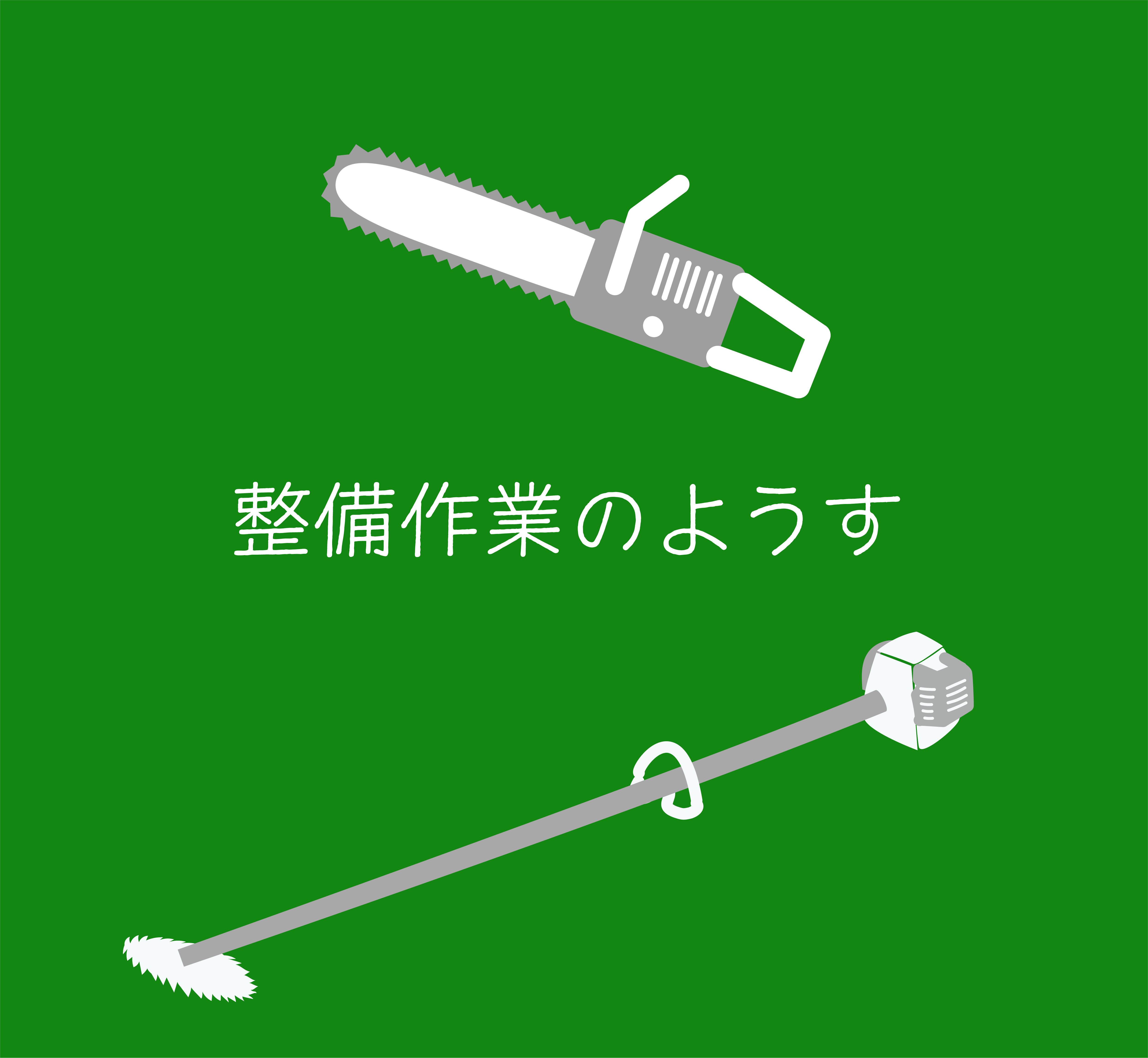


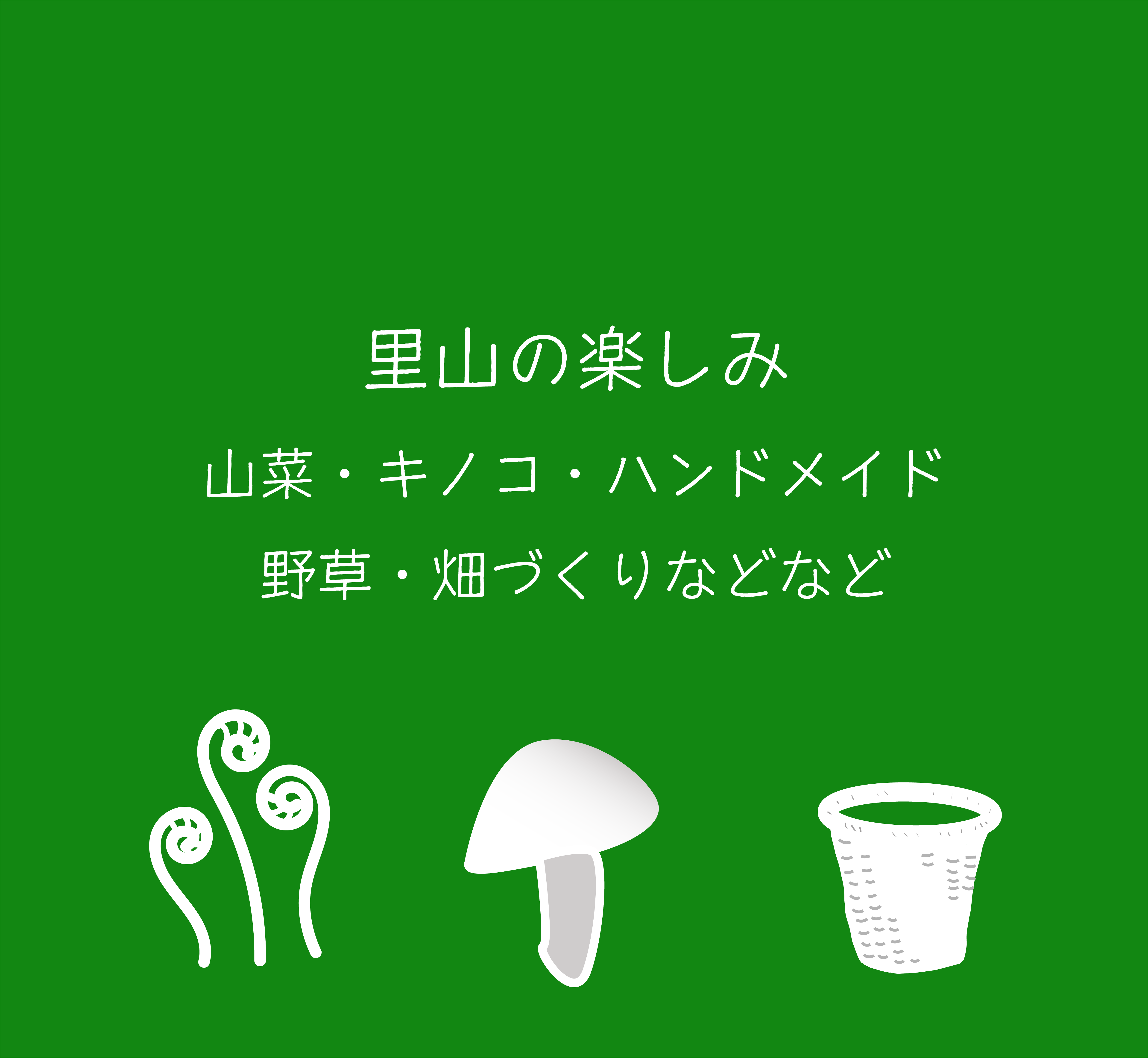


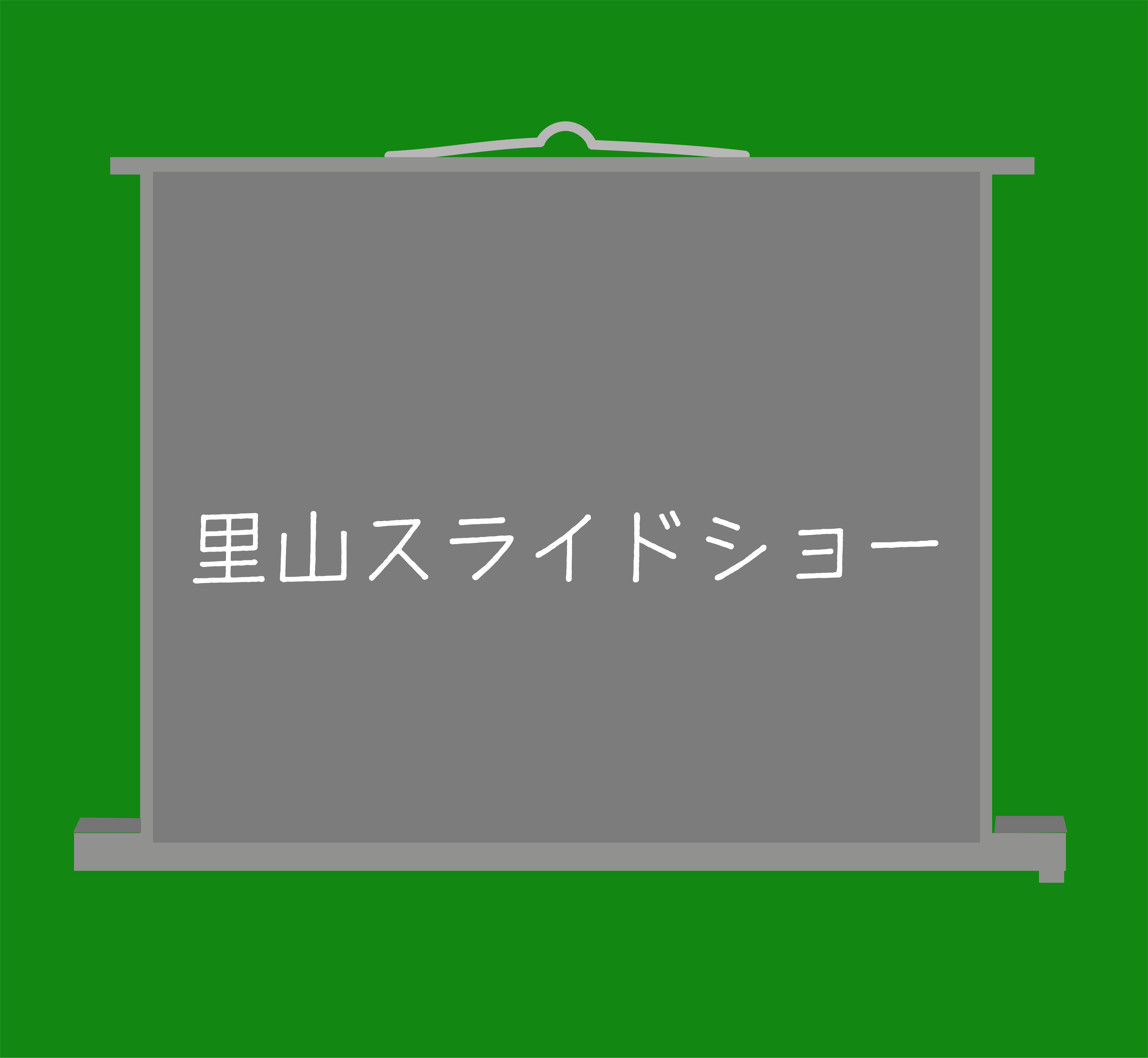
コメント